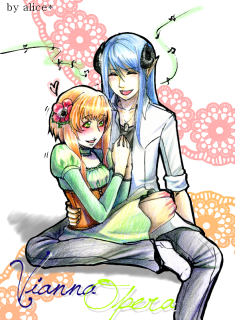
聞いたことのない言葉が紡ぐ不思議な詞は、聴いていて胸が躍るような旋律に乗って私の耳に届いた。
その心地好い歌声は、私を助けてくれた人のもの。
――もしも、足があったら。一緒に踊れたら…
そう考えて落ち込みかけた時、歌がふつと途切れ身体がふわっと浮き上がる。
お店が忙しくて草っぱらで少し遅めの昼食を摂っている最中だったから、食べかけのサンドウィッチを地面に落としてしまったかもしれない――ただ、驚いて目を閉じたせいで、落ちるところまでは見ていなかったのだけど。
「気にすんな。…足くらい、オレがなんとかしてやるから。」
「え…?」
胸に同じ匂いの髪がサラサラ流れ落ちてきたかと思うと、ぶっきらぼうな彼の声が降ってきた。そして返事も待たずに暖かくてやわらかいもの…多分唇がおでこに触れて少し鼓動が早くなるのを感じながら、硬く瞑っていた瞼を恐る恐る開けた。
「あのさ…いちいち自分責めるなって。…折角オレが歌ってんだから、もっと笑えよ。」
「…はい。」
自信に溢れていて、それなのに、余所見をするとすぐに拗ねる…今もきっと少し拗ねているから、もっと歌ってと言う様に笑って返事をした。
太股に私を乗せたまま座り込んで歌いはじめたのは、さっきと違う歌。やっぱり何を歌っているのか解らないけど、話す声とは全く異なるキラキラ透き通った声は鳥が恋人を探してる声みたいでとても心地好かった。
「……なあ、」
突然心地好かった歌が止んで、またあの声が落ちてくる。
「はい??」
「あんま褒めるな。……何か、恥ずかしーだろ…」
「…ふふふ…」
「な、なんだよ!?」
「何でもないです…。」
つい笑ってしまったのがばつが悪くて、隠すように彼の胸に顔をうずめて彼の心臓の音を聞いた。
どんどん早くなる鼓動が…破裂しそうなくらい一生懸命に脈打つ心臓の音が彼の胸に押し当てた私の耳に響いていた。
あの時みたいに早鐘を打つリズムを聞きながら、忘れられない言葉がリフレインする。
――足なんていらねーよ。んなもんなくたって、オレがどこでも連れてってやるから。
ここはもう奴隷市場ではないのに、毎日曇ったカオをしているオペラにそう言ったヴィアナは少し乱暴に彼女を抱きしめ、顔を一瞥もせずに鮮やかな色の髪をぎこちなく撫でた。
「あの、さ。」
何か言いたそうなヴィアナの目が驚きからか涙を浮かべたオペラの顔をじっと覗き込み、いつになく慎重に言葉を選びながら言う。
「お前が笑う顔、もっと見たい。毎日泣きそうな顔してんのはヤだ…。」
偶発的で稀な笑顔ではなく、毎日毎日笑う顔が見たい…しかしどうすれば笑ってくれるか解らないとも言い、長い睫を濡らす涙の粒を袖口で丁寧に拭い逡巡してから額にキスをし、もう一度…今度はとても優しく彼女を胸に抱きオペラのために歌を唄う。
ただ一言「好きだ」と言えればいいのに、それすら上手く伝える自信がないのは落ちこぼれだから――けれど言葉ではなく音でどこまで伝わるのか解らなかった。
二人でひとつだと信じていたヴィオラにすら伝わらなかった想いが、赤の他人であるオペラに通じるのか。伝わったとして、目も合わせてくれない彼女は自分を受け入れてくれるのか…。
けれど怯えて涙を浮かべる顔を見るたびに、笑ってほしくて気の利いた言葉を探していたが、思いつくものはどれも曖昧でその場凌ぎにしかならない気がして、いつからか口をつぐんでしまっていた。
大嫌いな「唄う」という行為を藁にもすがる思いで選んだのには、そういった理由があったからだった。
最初はどうでもよかった。呼ばれて、願いを叶えて、美味そうな宝石を奪って終る筈だった。気付いたら、ずっとずっと前に失くした片割れがそばにいるような、ちぎれてバラバラになった心が継ぎ接ぎながらに繋がったような気がして。
――笑って、笑って…いとしいひと。
言葉にすれば空ろになってしまいそうな想い。何よりも独りよがりのその歌がもしオペラに届いたら…いや、気持ちが伝わらなくてもいいから、今はただ笑ってほしかった。
「――‥…」
唄い終わって、呼吸を整える。そして恐る恐る彼女の顔を覗き込むと、
「…笑えるじゃん。」
その表情にひどく安堵した。でもそれは満面の笑みではなくて。長い睫に縁取られたきれいな青い瞳に次々と涙の粒を盛り上がらせて、涙が溢れないよう必死にこらえながら口角を持ち上げてオペラは笑う。
「――、笑って、って…聴こえたから‥」
けれどすぐに大粒の涙が頬を伝って流れ落ち、自分の意思では止められなくなってしまったようだった。
ヴィアナは呆然とその姿を見ていたが、突然オペラの姿が歪んで見えて我に返る――オペラと同じように溢れる涙を指先で撫でて確認し、すぐにその涙を袖で拭って彼女を抱きしめた。今はただ、そうしていたかったから。
「…その、言葉じゃうまく言えねー。形にしたら、嘘になったり壊れたりしそうだし……あー!もう何て言やいいんだ…」
自分自身の心に渦巻くものを言葉にできず戸惑っているのに、これ以上何て言えば彼女に伝わるのか今はわからなかった。
「でもオレ、もっとお前が笑うの見てたい…。」
ぐちゃぐちゃに混乱している気持ちの中で、これだけは確かだと言えるほどはっきりとした願いだった。
「オペラの笑顔が見たい。ずっとずっと傍にいて、お前の笑顔見てたい…このまま、ずっと傍にいてもいい?」
「は…はい…」
嗚咽交じりの消え入りそうな声で返事をしたオペラを抱く腕に自然と力が入ってしまうほど、その返事ひとつで受け入れられたのだと感じヴィアナは嬉しくてたまらなくなる。
未だ涙をぽろぽろ零して泣くオペラに戸惑いながらも、張り裂けそうな胸の痛みを溢れそうな涙と一緒に抑え込むと彼女の額に触れるだけの優しい口付けを落とした。
その日から、ヴィアナさんは毎日唄ってくれるようになった。
ほんの少しの時間を見つけては、喋るよりずっと長い時間を「歌」に割いてくれた。それはとても優しい歌声で、普段のぶっきらぼうなヴィアナさんとはまるで違う姿を連想させる。
「オペラの笑顔を見ていたい」…その想いに応えるのが精一杯の私を優しく包んでくれる歌声と、不器用だけど飾らないまっすぐな言葉が私に生きる力をもたらしてくれる気がした。
「…もう帰るぞ。今日はもう店おしまい。」
オペラが少し前のことを思い出しながらヴィアナにしがみついていると、彼はオペラを抱いたまま突然立ち上がり自分の店を閉めて帰ると言い出した。
「…?どうしてですか??」
それを不思議そうな様子でなぜかと聞く彼女にヴィアナは殊更照れた様子で、もごもごと口ごもりながらも理由をつぶやいた。
「義足、探しにいこ。腕のいい職人知ってるから…」
瞬間、オペラの顔は喜びと申し訳なさとで複雑な表情に染まり、最後には涙をぽろぽろ零し始めたので、ヴィアナは慌てて付け加えた。
「…オ、オレがそうしたいんだから!お前は笑ってろって!!」
そう口走った直後に言葉の選択を誤ったと言わんばかりの苦い顔をしたが、当のオペラはあまり気にしていない様子だったのでヴィアナは内心ほっとしていた。
聞いたことのない言葉が紡ぐ不思議な詞は、聴いていて胸が躍るような旋律に乗って私の耳に届く。
その心地好い歌声は、私を大切にしてくれる人のもの。私に笑ってほしいと言ってくれる人のもの。
――私を笑顔にしてくれるその歌声を、私はずっと傍できいていたい。今はただ、そう想う。
【おしまい】
*---------------------*
義足を手に入れたら、靴を買ってあげよう。いつか一緒に踊ってくれるように、きれいな飾りの付いた靴。
という一文はちょっとボツ(笑)
(私が二人を)好き過ぎる気持ちが強すぎて話が先走りまくりで、内容が激しくとっ散らかってしまってますがお許し下さい(コラ
■オペラちゃんは、モバゲーで仲良くさせて頂いてる「丹波さん」という方のお子様です。イラストは交流絵として出させてもらったalice*の作品になります■
